慶應義塾大学医学部の小児科教授である高橋孝雄医師によるWeb子育て相談。今回のテーマは、高橋先生の専門である「発達障害」についてです。一般的に発達障害がある子どもは、落ち着きがなかったり、コミュニケーションや対人関係をつくるのが苦手だと言われています。しかし、いったいそれがどんなものなのか正直よくわからないという方も多いことでしょう。また子どもがもし発達障害と診断された場合は、親としてどのように行動すればいいのかも気になるところ。一児の母で、発達障害と診断された甥をもつ、出産準備サイト編集スタッフKが高橋先生に伺いました。
(本記事はミキハウス出産準備サイトにて2017年4月17日に配信された記事の再掲となります)
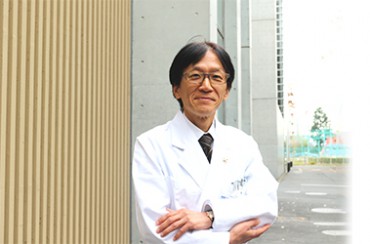
- 高橋孝雄(たかはし・たかお)
- 慶應義塾大学医学部 小児科主任教授 医学博士
専門は小児科一般と小児神経。
1982年慶應義塾大学医学部卒業後、米国ハーバード大学、マサチューセッツ総合病院小児神経科で治療にあたり、ハーバード大学医学部の神経学講師も務める。1994年帰国し、慶應義塾大学小児科で現在まで医師、教授として活躍する。趣味はランニング。マラソンのベスト記録は2016年の東京マラソンで3時間7分。別名“日本一足の速い小児科教授”。
発達の途中で症状が明らかになるのが「発達障害」

K:「発達障害」という言葉は、今の親世代が子どもの頃にはあまり聞かなかったように思うのですが、どういう症状を指すのでしょうか。
高橋先生:前回の連載で、生後12か月間の“発達”で「言葉によるコミュニケーション」「2本の足で歩く」「小さな物を指でつまむ」という3つの機能を獲得するとお話しました。「発達障害」はこれらの発達が遅れること指していると思われている方もいるかもしれませんね。でも、その場合は「発達遅滞(はったつちたい)」と呼ばれます。「発達遅滞」と「発達障害」は別のものなのです。まずこの点をご理解いただきたいと思います。
K:では発達障害とはなにを意味するのでしょうか?
高橋先生:自閉症だったり、注意欠陥多動症、それから学習障害などを総称して指す言葉です。一般には社会に溶け込みづらい人のイメージがありますが、それはある意味、正しい理解です。もう少し詳しく解説すると、「発達」するにしたがってだんだんはっきりとしてくるコミュニケーションや行動パターンの問題のことなんですね。つまり発達遅滞と違って、生まれて半年、1年で発達障害か否かを判断することは非常に難しいです。言葉でコミュニケーションをとる年齢になり、集団生活の場が増えるにつれて「この子の問題は言葉の遅れというよりはコミュニケーション全般の問題なのかな」「知能が遅れているのではなく、あまり考えずに行動して落ち着きのないことが問題なのかな」などと思い当たるようになるわけです。発達“遅滞”が文字通り発達の遅れであるのに対して、発達障害は発達するにつれて明らかになってくる問題という意味です。

K:発達の途中で症状が明らかになるということは、生まれつきというわけではないのですか?
高橋先生:発達障害の多くは持って生まれた強い個性のようなものです。ただ、生まれてしばらくは生活の範囲が狭く、社会生活で問題となる強い個性が発揮される機会もないので、それに気づかれにくい。活動範囲が広がりいろいろな場面に遭遇すると、どうも落ち着きがないなとか、どうも衝動性があるなと周りが気づくようになるわけです。
K:そこで初めて「あれ、発達障害かも?」と認識するというわけですね。
高橋先生:ええ。成長して行動範囲が広がり、人とのコミュニケーションができるようになった時点で、少しおかしいことに気づくものなのです。もちろん通常は、人生で最初のコミュニケーションの対象はお母さんやお父さんですね。他の例をあげると自閉症の特徴として良く知られているものに「目が合わない」という症状があります。でも、生まれたばかりの赤ちゃんは目で物を見つめることをしませんので、目が合うも合わないもないわけですね。「あっ、私と目が合うようになってきたな。見つめてるな」とお母さんが感じるようになるのは生後1か月ごろのことです。
K:なるほど、そういうことなのですね。お医者さんが発達障害という診断を下す際、明確な基準はあるのでしょうか?
高橋先生:診断のための基準はあるのですが、だからと言って、客観的に、断定的に診断がつくものではありません。他の障害と同じように、症状が強く、典型的に表れている場合と、そうでない場合がありますからね。無理に診断を付けようとせず、病名をつけることにメリットがあるときに、必要に応じて診断名をお伝えすれば良いと思っています。
K:といいますと?
高橋先生:病名をつけることで救われる人に対しては、伝えるということです。ある男性は、病名を知ったことで「内なる敵がわかった。自分で行動を変える努力をしたり、訓練である程度克服できる病気だとわかって良かった」と言っていました。
K:病名を伝えられることで前向きになれるタイプの方もいるということですね。

高橋先生:一方でデメリットに感じる人もいる。自分ではさほど気にしていなかったのに、まわりから「君はアスペルガー障害のようだね」と言われる。自分では、口が重くて、仲間に加わるのが苦手なだけだと思っていたのに。
K:そういう人にとって病名をつけられることは、レッテルを貼られることに感じてしまうかもしれませんね。
高橋先生:そういうことです。ご両親にとっても同じことです。診断基準は診断を付けるための目安であって、ここからが発達障害で、ここまでは正常といった線引きはできません。患者さんやご家族にとってのメリット、デメリットを良く考えてから、診断名について触れることが大事だと思うのです。
K:ちなみに私の妹は、息子の衝動性や攻撃性にほとほと困っていて悩んでいたのですが、医療機関で発達障害と診断され、ホッとした様子でした。「私の育て方が悪かったわけでないんだ、この子の個性なんだ」と安心したと言っていました。
高橋先生:それは病名がついてよかったケースですね。










