1980年代から社会問題化した子ども同士のいじめは、1990年頃から減少傾向にありましたが、この数年は再び増加しているようです。特に小学校での増加が目立つという調査結果(※)は、これから学童期を迎える子どものママ・パパにとっては大いに気になります。そこで、子どもの社会でのいじめについて、慶應義塾大学医学部教授で小児科医の高橋孝雄先生に伺いました。
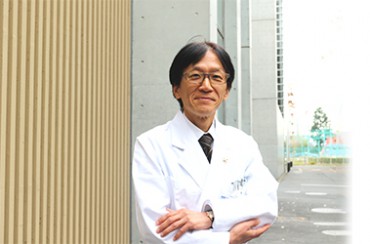
- 高橋孝雄(たかはし・たかお)
- 慶應義塾大学医学部 小児科主任教授 医学博士
専門は小児科一般と小児神経。
1982年慶應義塾大学医学部卒業後、米国ハーバード大学、マサチューセッツ総合病院小児神経科で治療にあたり、ハーバード大学医学部の神経学講師も務める。1994年帰国し、慶應義塾大学小児科で現在まで医師、教授として活躍する。趣味はランニング。マラソンのベスト記録は2016年の東京マラソンで3時間7分。別名“日本一足の速い小児科教授”。
「残念ですが、いじめのない世界はありません」

担当編集I(以下、I):2020年秋に公開された文部科学省の調査結果(※)に、いじめの発生件数のピークは小学2年生という報告があり、低年齢化が進んでいる現実に驚きました。もっとも調査では「いじめ」の定義が広がり、ひやかしや悪ふざけなども含まれたことも一因ではないかとも言われています。とはいえ、ママ・パパにとっては心配な状況といえるかもしれません。ということで今回のテーマは「いじめ」。自分たちの時代にも大なり小なりあった子どもの社会のいじめですが、これを根絶することはできないものなのでしょうか?
高橋先生:残念ながら、いじめのない世界はないと思います。みんなが横一線、利害もぶつからず、意見もぶつからず、上下関係もない、そんな社会はおそらく存在し得ない。問題は程度であり、受けた側がどう感じているか。これ、「ハラスメント」の問題にもよく似ています。
以前、医学部の研修でハラスメントについて学ぶ機会がありました。その内容は「どういう意図による言動かではなく、相手がどう受け取ったかでハラスメントか否かが決まる」、「たとえ言われた本人が『その指摘はもっともだ』と受け止めても、その場に居合わせた第3者が『やりすぎだ!』と感じたらハラスメントになる」など、あくまでも相手や周囲の受け止め方によって判断されるというものでした。いじめもハラスメントも、相手の気持ちや周囲の感じ方が、その判断基準ということです。
I:いじめかどうかは、いじめられた方がどう感じたかで決まるということですね。
高橋先生:そうです。でも、幼い子どもたちの世界にあるのは、(大人の社会であるような)本当の意味でのいじめではなくて、いじめに至らない“小さな争いごと”、つまり“いざこざ”がほとんどでは。保育園、幼稚園の年頃だと、ふざけてからかったり、ヒソヒソと内緒話をしてみせたり、大人が眉をひそめるようなことをする子もいます。ささいな事で意地を張り合う、モノを取りあうといった“いざこざ”も日常茶飯事でしょう。

I:そういうことがあると、親としてはわが子がいじめられているのではないかと不安になるわけで…。
高橋先生:子どもの社会には、“健全ないざこざ”と呼べるようなものが多いのでは。例えば、3人でひとりをからかっていても、傍から見ていてちょっとやりすぎかなと思うような悪ふざけでも、いじめとまでは言えないものも多いのかもしれない。
「これを放っておくといじめになるのでは?」と心配する親御さんの気持ちは分かります。でも、大人はできるだけ口を出さずに見守ってみてはいかがでしょうか。子どもたちには友だちとの遊びの中で、いざこざを通じて人間関係を学んで欲しいですね。それは貴重な経験だと思います。










